えんすけっ! 藤澤桃里の一昼夜物語

「――あと、これだけっすか!!」
ぼんやりとわずかに青味がかった冷たい感じの明かりの下で藤澤桃里(ふじさわ ももり)は紙の束を目の前にして、ぱったりまぶたをつむりながら叫んだ。
窓の外では晩い夜の空気の中で小さく虫の鳴く音と、時おり近くの国道を走るトラックの音が聴こえるくらいで、辺りは静かなもの。声が無くなったときが静かすぎるので、その落差からなのか桃里の叫び声はあまり響かずにシンと消えてしまった。
桃里の目の前にぱさぱさと何枚か控えている紙の束は、白いものもあれば、プリントアウトされた行の隙間のほぼ無い単調なテキストの団体が印字されたものもある。
真っ白いのは、まだ内容のプランをたててないまんがのおおまかな内容などを描こうとしている紙――。テキストの団体が刷られてるのは、大体こんなような内容を考えたからいっしょに描いてくださいなどなど、ほかのひとといっしょに描くものの設定やら決めぜりふやらが記されてる紙――。
藤澤桃里は、悟徳学園の漫画研究会でつくってる同人誌などに主にまんがを描いたりしてるが、それ以外にも友人、知り合い、中学の同級生、その同級生のファン、とおい親戚、袖すりあうも多生の縁な人などなどなど……、いろいろな方面にわたって首を突っ込んでる部誌・会誌・個人誌好きニンゲン。一個一個はプチサイズでも、その総数はおびただしいことになっている。
ぺらぺらぺら……と紙をめくり、そしてその中から、必要な個所におおまかな展開を引いた箱書きや、登場人物の特徴などの絵をつけ終えた何枚かを選り分ける。
「――まだあと、これだけっすか!!」
しかし、そんな態度と声とは裏返しに、メガネごしの目にはあせりの色などは浮かんでいない。
余裕があるというわけではないが、どうにかこなせるだろう、という楽観が垣間見られるのだった。
藤澤桃里は早起きだ。
昨日の晩、あれだけ紙の束といっしょに夜中おそくまで目の玉と腕と脳神経とを突き合わせていたけけども、いつもとおなじぐらいの時刻には起床して、ガシャガシャと歯みがきをしている。
まだ紙の束の内容を考えてるのかと思いきや、午前4時過ぎの明るさの中、洗面所の脇から見える庭の背の低いモミジの木の葉を眺めながら〔今年もいい色になるかな〕――と、考えているだけ。
「(ガシャガシャ)もみじ……(ガシャ)昼夜の気温差で色のグラデーションするもみじな練りハミガキがあったら(ガシャガシャ)即買いっすね……!!」
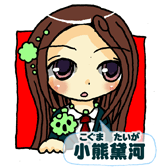
「練り歯みがきにそんな幻覚を見るなーッ!!」
朝の悟徳学園の廊下に小熊黛河(こぐま たいが)の声がスッと通りぬけた。
「えーっ、みやびやかでイイと思うんすけど。朝は赤かったり、夜は黄色かったり……」
「歯茎から血が出たときに赤いとーッ、わかりづらい」
そう言いながら黛河が廊下を曲がって自分の教室に入って行くと、桃里もその後ろに一緒になってついて行く。
小熊黛河は藤澤桃里とはクラスが別だが、以前に桃里が描いたヨーロッパの火の玉がいっぱい登場してる漫画研究会のポスターをたまたま見かけて火の玉の絵についてしゃべりかけて以来、よく話をしたりする仲の友人だ。
黛河は火の玉自体に興味があってグングン燃えて突撃をしたわけではなく、桃里が描いてたおしゃもじ型の火の玉や、ハンス・テグナーをオマージュして描いたいろいろな顔がついてる火の玉の絵に対して〔これはどういうエクトプラズムだろう〕と不思議に思って、尋問に行ったというのが接触の動機だったが、いろんな方角からトストスとしゃべる桃里のことをおもしろく感じて、いつの間にか朝のホームルームがはじまるまでの時間帯などに会ったらよくしゃべったりする間柄になっていったのだった。
教室の中に入ると黛河は窓側列一番奥の自分の席に坐り、カバンを机のわきに掛ける。
桃里は窓辺に背中をつけてその脇にたたずむ。
「あら小熊さん、また一番うしろの席を席替えで獲得したんすか?」
「今学期もここからクラス全員の授業中の心理行動をーッ、眺めてたのしむわけ」
黛河はカバンの中から数冊ノートを取り出すと、その1冊をくるくるとまいて遠眼鏡状にしてクラスの中を見渡すようなしぐさをする。
まだ時間も早く、部活動の朝練がある面々はそっちに動いてる頃合いなので教室の中にいるのは、このふたりだけ。
「かーッ、変態っすね」
「やっと変 熊 って言うのあきらめたね、桃里さん。それ正しいよ」
ノートくるくる巻き望遠鏡で桃里を間近にのぞく黛河。
「……字で書くほど言いやすくは無いんすもん!へんゆー……、へんぐま……」
「HEY YOU!みたいに聴こえて変すぎ」
そう黛河が言うとコクコクと首をたてにうなづかせながら桃里がノートくるくる巻望遠鏡に顔をくっつけて、向こう側からのぞきこむ。
「でしょう?そうっすよ、へんぐまだと、〔ヘミングウェイ群馬に行く〕の略みたいだし……、やっぱり口で発するにはつらいっす!!」
「そっちのほうがうれしいよ! ヘミングウェイの略し方に無理がありすぎるし」
「そうっすか?」
「それだったら〔天狗魔に似てる〕とか無難なところで来るのがいいかんじに収まりがつくでしょーッ」
「あぁ、昨日の晩に協力原稿のテキスト文の中で何度もベルムーテスってのを見たんすよっ、それで何となくヘミングウェイがしゃしゃって出て……群馬県と……」
「それは!ぜんぜんヘミングウェイと音が似てない!!」
黛河はノートを机の中にしまいながら応酬するが、桃里は真顔で淡々とそれを受け流す。
「"ベルムーテス" は "バミューダ" から語の響きが由来してる魔族の島っすから!! ヘミングウェイが憩ってた島とつなが……そういえば小熊さん、島に行ったとか言ってなかったすか!?」
この切り返しの乱雑さと、その直後にぶち刺さってくる不規則な話題変化が黛河にはちょっとおもしろみのツボらしく、顔に表情として浮上はさせないが、感情の芯ではすごくニコついてるのだった。
「あぁーッ。夏休みにね、越後の親戚の家にいったとき佐渡にいったよ」

昼休みの悟徳学園の校庭の一角に並んでる梅の木の下に坐って、町田花眠(まちだ かみん)はデジタルギターをつかって佐渡おけさをピコピコとアレンジしている。
「え? 桃里っちゃん何ていうひと? ひと?」
「だーかーら、グレトリっすよ! グレトリ!!」
桃里は例の紙をじーっと見つめながらその隣に腰をかける。
「♪どーこーのーーグレトリちゃーんっ?!」
突然佐渡から木曽に南下して、"木曽のおんたけさんはー" のメロディにのせて訊いてくる花眠。
「ベルギーじゃホイ」
桃里が木曽節にあわせて答えると、花眠はデジタルギターから手を離してうーんと腕を組み出す。
「で? 桃里っちゃん、そのベルギー生まれのグレトリちゃんって作曲家が、ほんとにこんなようなインスピレーション発想方法をしてたのっ?! まじめ?! まじめ?!」
そういいながら花眠がパッと両脚を持ち上げる。靴下はつけておらず、足の裏にはお弁当と一緒に入れておくためのてのひら大くらいの保冷剤がそれぞれハンカチでしばりつけられている。
「小熊さんが今朝そう言ってたから間違いない」
花眠と桃里は、黛河から教えてもらった18世紀の作曲家・グレトリが曲づくりのインスピレーションを得たいときにしばしば行ってたという〔両脚を冷やす〕を実践してみているのだった。
「そう言ってたって……またぁ、グレトリちゃんがばりばり作曲してた時代は、日本で言えば田沼意次の時代でしょ〜、保冷剤無いよ!!!」
「冷やしてたんすよっ!! ……氷水に脚をぶちこんでたってのが本来っすけど、氷をもらってくるのは手間っすからね、原理としては間違いないはずじゃないっすか……?」
「わっからないよ〜〜、温度より水分のほうがインスピレーションへの刺激の比率が高かったら、この方法ではダメかも知れないよ〜!」
「それも……そうっすね」
「そうっすよ」
花眠はそういうと脚を靴に戻して、デジタルギターを背中にまわすと立ち上がった。
「あっ、桃里ちゃぁぁぁん、どうして花眠ちゃんと一緒にさっきからジャージすがたなのぉ?」
帰りのホームルームの直前、今野円(こんの まどか)が桃里の近くにぱたぱた駈け寄って来た。
「へっぷしゅ、へっぷしゅ、へっぷしゅ」
早速、返ってきたのは3連発式の桃里のくしゃみだけだった。
「おい、まどか、改めて訊くまでも無いだろ」
「えぇー、あきちゃぁぁぁん、だって気になるよぉぉぉーーーー、くしゃみヒューマンに変貌しちゃってるしぃ、分かちあわないとぉ」
口井章(くちい あき)に円がズルズルズルズル引きずられていく様子を眺めながら、桃里は〔そうか、ああいう風に鬼に兜を持たれてズルズルズルズル引きずられるシーンを描こう〕と、例の紙いちまい分のインスピレーションを得たのだった。
(2014.09.08 氷厘亭氷泉)