えんすけっ! 三人のハダシ


「あのトオりのヘビちンみたコとありマスか?」
へびちん――と称されてるのは、街の境目などに飾られるワラであまれた蛇のかたちの魔除けで、"辻ぎり"などと呼ばれているものである。
「そんなところ注目しながら公道を歩ってるのはこの行政区域ではネブしかいない」
赤柴水矢(あかしば みずや)はそう言い放つと同時に葱耜月世(ねぶすき つきよ)に向かって何やら白いものを投げつけた。
イルクーツクを流れるレナ河のような月世の長い金髪にぶつかったその白いものはペシャッと音をたててそのまま重力に従っていく。
「わァーーあ、みずっチ、ひどイよっ、"れしいと" なんかナゲて! モシからダとイッタイカしたら!! どウするノ!!」
「だって、わての坐ろうとした席にいきなり寄生生物してらしたんだものっ、その紙っきれ!!」
水矢はそう言いながらフードコートの真ん中あたりにある座席のイスを引いて、ポコッと腰を落ち着ける。
月世が足もとに墜落したレシートを拾ってから、その向かい側のイスを引いて、同じくポコッと席に就いた。
「……スタツ……」
「あーあー、紙っきれなんか拾って、やだなー、ネブ。――それに、いちいち読むんじゃねぇよ」
「だっテ、なんカ、トテツもなイ "れしいと" でシたかラ」
「とてつもないぃ?」
水矢はかかえていたプラスチック製の書類ケースを座席のテーブルの上に置くと、月世の眺めているレシートを覗き込むように首をのばす。
「みこセマせんヨっ〜」
頭上のほうへヒョイとレシートを高く持ち上げる月世。
その動きに合わせてアクロバティックに顔を動かしてのびあがろうとも思ったが、水矢はそれをのびあがり実行未遂にとどめた。
いくら周囲の座席に坐ってるのが、わかめうどんをもくもくと食べてる老夫婦と、黒背革の手帳の中身と睨みあってる何かのセールスとおぼしき若い女性だけで視線は自分たちにはそそがれないといっても、理の字と性の字は仕事を全うしていたのだった。
「……スタッ……」
頭上にあげたままのレシートを片目をつぶりながら見ている月世。
「もうっ、なんなんだよ、その"すたすた"だかっ、"ずたずた"だかいうのはっ!!」
水矢がテーブルの上にべたんと倒れ込むように体をのばしてレシートのほうを顔を少しでも近づけてのぞき込もうとすると、月世はするするするとレシートをその目の前へおろして来た。
「さテ、この"れしいと"をスてたヒトは、なんコ、こノ商品をカっているデしょうか」
「ややっ……久しぶりの "すぱい くえすちょん" だな」
「だカらー、諜報かツどウはしてナイっでスってばー」
レシートを持っている月世のゆびで、ちょうど購入個数の数字は隠されている。
「……それはそれとして、このレシートのぬし、何買ってるんだ?」
水矢は、わざとらしいロシア訛り(?)で否定をこころみた月世の持つそのレシートの印字に目の玉の焦点をあわせていく。
「……ス……? ……スタ……、ああ、スタ゛……なんだ、ネブ。これ "ツ" じゃなくて "ダ" の濁点の部分じゃねえか!!」
「あーソうとモ、ソうとモ」
「そうやって民謡みたいな口振りを混ぜることによって日本人から情報を引き出そうとしても無駄だぞっ」
「いいかラ、あてテ、あテて!! なんコ?! 何個?!」
うきうきリズムをとりながら、レシートを持ってないほうの手で水矢の肩をピアノをひくような指づかいでわさわさする月世。
テーブルの上にもたれかかったままの姿勢で、「んーーーー」とほんの10カウントぐらい、熟考する水矢だったが、パチっと花弁がひらくように口を開けて答えを放つ。
「――2つ!!」
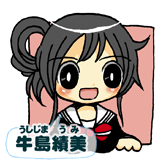
「あははは、ぜんっぜん想像できないと思うよ」
月世と水矢がレシート数字当て大決戦を行った直後にやっと集合した牛島績美(うしじま うみ)は、フードコートの座席に微笑みながらドサッと着地した。
「ほら見ろネブっ! ぜってぇわかるわけないだろっ!!」
「えエぇっ〜〜〜、でモはじめニ、余は、トテツもなイ "れしいと" だって認証宣言しタじゃないデすか〜」
「そりゃ、言ってたけど、限度があるだろっ!!」
「あははは、で? みずっちはレシートに何個って打ってある予想したの?」
「わてはな、きちんと筋道たてた考察をしたうえで、2つと導き出したわけだ!」
堂々と、にほんゆびを付き出して績美の笑い顔に向けて数の主張をする水矢。
「考察って何、どんなお買い物だと想像したわけっ? あはは」
「……すだちなんてどんなに頑張っても1個くらいしか買わないだろっ? わかんないけどさっ。でも、もし商売とか何かで大量消費するとしたら定期的に買いにくるうだろうから一挙に山のように買うとは思わなかったんだよっ、それで、3〜4と考えたんだけど! だけど! あえて2に調整して、そう答えたわけだ!!」
「商売とかで使うって考えたんなら、逆に数を多くすればよかったのにー」
「そウー、牛ちゃんのサイズのようニー、数大きくー多クー」
月世が績美の近くにイスを引っぱり寄せながら言う。その視線は明らかに績美のバストへと流し遣わされていた。
「そんなこと言ったって、わかるわけねぇだろっ、だいたいどこの個人客が一気にすだちを29も買うだなんて答えられるかってんだ!! それも、すだちひとつっきりで他には何も買ってないような客っ!!」
水矢はそう言いながら、書類ケースの中からルーズリーフを挟む形式のノートを取り出して績美に手渡す。
今日の主要な目的、夏休みの間におのおのが折口忍に遭遇した際の言動行動などを箇条書きしたかなり "スパイてき"メモの交換をしているのだった。
「あははは、みずっち……すごいじゃん!! 忍さまと本屋でまた遭遇できたのっ?」
もともと、折口忍は個人誌なども気がむいたときにしか出したりせず、何か活字にプリントするとしてもチョロっと薄いものしか手掛けたりしないため、常に忍まにあの三人はその言動などにも貪欲なのだ。
「今回は、雑誌は上から3冊目だけをひっぱり出して選んでたよっ!」
「週によって違うのかなぁ……あははっ、でもそれ単にその雑誌の積んであった数が多かったからなんじゃない?」
「それもあるかもしれない、余が見かけたそのときはその雑誌たしか……発売日だったし……! ――おいっ、ところですだち経済学者はどんな報告あるんだっ!?」
水矢がそう言って月世の顔をムッと眺めると、月世はハッと目つきを変えて手でバンとテーブルをひとつ打つ。
「すダち経済学者は、忍さまとへビちんを触ったノです!!」
「えっ、そうなのネブ?」
「それでさっき、どっかの通りの蛇だとか言ってたのかっ?! ネブっ?!」
績美も目の色を輝かせているが、水矢の目の色も十何分か前に月世が「ヘビちン」と言っていたときとはずいぶん変貌していた。
小さなろうそくの明かりのもとで静かに闇と溶けるワインの赤むらさき色が、果てしなくきらめく南国のサンゴ礁の太陽の下のブルーにザッとスイッチコンデンサひとつで変わったかのようなハッキリ分かる変貌である。
「そウですヨ。余があの車通りノかなあみの塀ノとこロにぶらぶら居るヘビちンの様子を見ニ行ったラ、お遭いシたのでスヨ」
「ネブっ! なんでそのとき誘わなかった!!」
「余がへびチんの夏の容体ヲ拝みニ行きまショーって言ったトキ、みずっちは丁度……」
「あ、おぼえてるおぼえてる、そんなことネブが言ってた日、あれだよ! あはははは、みずっちはあれだよ! "本棚にある柳田先輩の個人誌を順番に並べようと思ったら1個どこにいったのかわかんなくなった!!" とか地獄のようにうめいてた日だよ!」
そう言いながら、績美は集合する前に買ってたのかソーダ味のカップ入りシャーベットをテーブルに置き、しゃりしゃり食べ始めた。
「……あれか……、あれが無けりゃ……わても、もしかしたらわてもそんなバカらしい遭遇点に立ち会えたのか……くそぅぅぅ」
「みずっち、結局あのときの見つからなかった本はどこにあったの?」
「その本棚のすぐ隣の箱の上に積んであったんだよッ!! ――でっ?!! 蛇んところで忍さま何か重大発言してたりしたかっ?!!」
「あのネ、ヘビちン、ワラがぼそぼそに乾イてテね、余が"コのへびチんは、じゅうわりそば ノようなぼそぼそさデスナー"て言ったらァ」
"辻ぎり"は毎年1月ころに配備されるので、もうこの夏の終わりの時期になると風雨にも完璧にさらされまくって、相当すがたかたちは、あわれモードにさしかかってるのであった。
「なんだその糞たわけな表現は、ゼロ意味に近いぞ、そんなこと忍さまに向かって発したのか、こらっ!!」
「まぁまぁ、で? みずっちはこう突っ込んだけど、あはは、忍さまはどう突っ込んでくれたの? くれたの?」
績美がシャーベットを乗せた木さじを水矢の怒りの口先に突っ込ませながら訊く。
「そしたらァ忍さま、へびチんのぼそぼそノわらヲさわッてー"これは、はだしで壁土をごそごそしてるみたいだわ" っテ……あっ! ふたりトもどこ行く?!」
「ばかっ、いまからすぐに牛ちゃんの部屋いって、みんなではだしでつちかべごそごそ体験するぞっ!! 比較記事展開だっ!!!!!」
(2014.08.31 氷厘亭氷泉)